▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます
・目白の風景 今昔:目次
・吉祥寺の風景 今昔:目次
・昔と今の写真(番外編):目次
・地中海バブル旅行etc.:目次
・旅のつれづれ:目次
・母のアルバム:目次
・目白ジオラマ鉄道模型:目次
・すべてのカメラに名前がある:目次
・目白の風景 今昔:目次
・吉祥寺の風景 今昔:目次
・昔と今の写真(番外編):目次
・地中海バブル旅行etc.:目次
・旅のつれづれ:目次
・母のアルバム:目次
・目白ジオラマ鉄道模型:目次
・すべてのカメラに名前がある:目次
Ricoh_Super44の試写 ― 2019年08月12日
(前回)からの続きです。
試写には以前買った市販フィルムを使用しました。
こんな風に巻き取りを開始し、
三角マークが所定の位置まで進んだら、
蓋をしてロックします。
ロック機構はしっかりした造りです。
「リコーフレックス 」の初期タイプは、ロックが甘めで、
途中で裏蓋が半開きになってしまったことがあります。
この辺りの機構は少しずつ改良されていったのでしょう。
蓋を閉めてカウンターに[1]の数字が出るまで送りました。
ちょっと引っ掛かりを感じましたが、その時だけで、
その後は12枚目までスムースに送れ、撮影完了。
しかし、フィルムを現像するために、
ダークバックの中で作業をしている時に異変に気付きました。
フィルムの端部がシワシワになっていたのです。
「ありゃー!これはフィルムがどこかに突っかかって、
全然送られなかったかもしれないな。
そうだとすると、現像しても意味ないな。」
でも、暗袋の中で、どういう状況か良く分からないし、
「まあ、いい加減で良いから、とにかく現像だけはしてみよう。」
と思い、液温管理もせずに、10分ほど現像してみました。
これでフィルム全体が透明だったら、
フィルム送りに不具合があったことになります。
ところが、結果は次の通り。
確かに第一コマ部分は、シワシワになっていますが、
何がしか写っている様子。
ここから類推するに、
巻き上げ時に、フィルムの先頭部分が正常に送られず、
本体とローラーの隙間に落ち込んで、引っかかったようです。
再現すると次の状態ですね。
このシワシワ部分は、その後、後続のフィルムに押し出されるようにして進み、
2枚目以降は普通に撮影できたのでしょう。
原因は、フィルムの製作不良、と判断しました。
そういえば、現像前にダークバックの中で、
フィルムと裏紙を分離させる時におかしなことがありました。
普通は、次のようにフィルムの先頭は裏紙に「テープ止め」されています。
両者を一体化して、巻き上げ時に一緒に進むようにしてるのですね。
一方、フィルムを現像する時には裏紙は邪魔ですから、
現像前に、このテープ部分を剥がしたりちぎったりして、
フィルムを裏紙から分離させるのです。
ところが、今回はそのテープを剥がす作業をしないうちに、
フィルムと裏紙が自然に分かれてしまったことを思い出しました。
実際、現像後のフィルムと裏紙を確認すると、
テープ止めされた部分に残るはずの「貼り後」はありませんでした。
そんな風にフィルムの先頭が固定されていない状態であれば、
その端部は、容易に本体とローラーの隙間にハマり込んでしまいます。
結局、カメラ本体と、私の撮影方法に関しては問題はなかったのです。
「なーんだ、それだったらきちんと現像すれば良かったな」
と思っても後の祭り。
夏場の水道水の液温のまま現像液を作って現像したので、
明らかに処理時間オーバーで画像部分は、ほとんど真っ黒。
本来、現像液の温度を下げるか、早めに現像を切り上げるかすべきでした。
ところが、この吊り下げたフィルムをよく見ると、
左側の5mmほどは、濃度が薄めでなぜか適正露出っぽいです。
「あれ!?何でこんなことになっているのかな?」
この原因は、すぐに分かりました。
「そうだ、液量を間違えたんだ!」
現像タンクの裏側にフィルムごとの液量が指示されています。
これによれば、127フィルムの場合は「370ml」です。それなのに、
使い慣れた35mmフィルムの液量「290ml」で現像してしまったのです。
だから、きちんと液に浸かった部分はオーバーになり、
濡れる程度で現像の進行が遅かった部分は、
皮肉にも「適正な結果」になったのですね。
ということで、今回の試写は、
・Ricoh_Super44
をチェックするつもりが、
・フィルムの製造工程
・現像時の私の注意力
のチェックをしたことになりました。
撮影画像は、一応スキャンして、
コントラストなどをPC上で調整した結果、
次のように、ある程度見られるようにはなりました。
ただし、この二枚を見ると、
少し「後ピン」傾向のような気がします。
これは、また後日、
カメラの整備をする時にチェックするつもりです。
果たして、カメラのピント機構の問題か、
あるいは撮影者の注意力の問題か。
(終り)





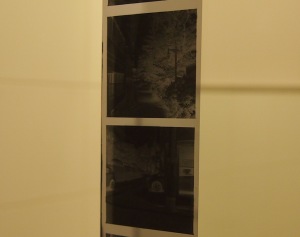



最近のコメント