▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます
・目白の風景 今昔:目次
・吉祥寺の風景 今昔:目次
・昔と今の写真(番外編):目次
・地中海バブル旅行etc.:目次
・旅のつれづれ:目次
・母のアルバム:目次
・目白ジオラマ鉄道模型:目次
・すべてのカメラに名前がある:目次
・目白の風景 今昔:目次
・吉祥寺の風景 今昔:目次
・昔と今の写真(番外編):目次
・地中海バブル旅行etc.:目次
・旅のつれづれ:目次
・母のアルバム:目次
・目白ジオラマ鉄道模型:目次
・すべてのカメラに名前がある:目次
GS645とAcrosで池袋 ― 2020年01月17日
これは法明寺の裏口です(多分)。
このカメラはブローニーフィルムで15枚撮りです。
普通このタイプは16枚撮りなのですが、
GS645は万一のコマ被り等を避けるために、
15枚に抑えているそうです。
それだけ「写真」にこだわっているのでしょうね。
そんな15枚の撮影と現像が済み、その中で、
私好みの一枚と言えそうなのが最初の「裏口」写真です。
随分と存在感のある裏口でしょう。
でも、実際にこの扉が開いて、
人が出入りしているのを見たことはありません。
使われることのない裏口ですが、
風格は、次の山門に負けていませんよね。
ちなみに、この山門の左手を池袋方面に抜ける次の細道に面して、
この裏口があります。
Rollei35で暮れの神楽坂と赤城神社 ― 2020年01月07日
ローライ35という、個性的で魅力のある、
でも、使いにくいカメラがあります。
どんな点が使いにくいかというと、
・まず携帯方法。
この写真のRollei35には、純正品のリストストラップと、
三脚穴にねじ込む方式のネックストラップの両方が付いています。
実際には、このうちどちらかを選ぶことになります。
カッコ良いのはリストストラップなのですが、
私は、撮影時以外は両手がフリーになるネックストラップが好みです。
でも、それを装着すると、
次のフィルムカウンターが隠れてしまって、
何枚撮影したか分からなくなってしまいますね。
・それから沈胴式レンズの格納方法
この写真の[A]ボタンを押しながら、
[B]を回してロックを解除してボディに押し込むのですが、
その前に[C]のレバーで一枚分巻き上げておく必要があります。
この[C]を忘れたまま押し込もうとすると、壊れてしまうのですね。
・そして、これは本当にどうかな?、と思うのが電池の収納方法
何と裏蓋を開けて、更に、
フィルムパトローネ収納場所の奥の蓋を開けて、
[+]と[-]の方向を注意深く見極めながら、納めなければならないのです。
このローライ35は英国のエリザベス女王の愛機でもあったのですが、
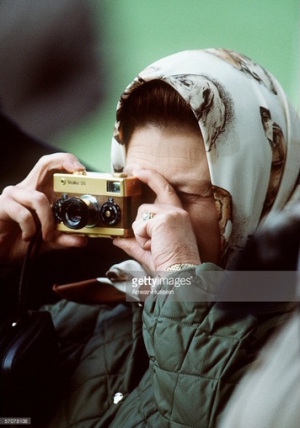
女王にこの作業をさせるのは酷ですよね。
(まあ、御付きのものが代行したのでしょうが)
と、そんなカメラなのに、時々、持ち歩きたくなります。
それは、このカメラが何とも「カッコ良い」だけでなく、
なぜか私好みの写真が撮れてしまうからです。
不思議なことがあるもんですね。
そして「年末年始はモノクロの季節」と感じている私は、
Rollei35にフジAcros100を詰めて、
師走の神楽坂に出かけました。
その成果。
次は赤城神社に移り何枚かパチリ。
それと、このカメラはフィルムを装填するのも面倒くさいのですが、
コンパクトなサイズのためか、上手に装填すると、
36枚撮りフィルムで、40枚も撮れてしまいます。
その辺は腕の見せ所で、うまく40枚撮れれば、自慢できますよ。
(誰も褒めてくれないけれど)
EL-Nikkorでオートフォーカス ― 2019年12月31日
(前回)からの続きです。
前回取り上げた「PentaxSV」+「EL-Nikkor 1:4 75mm」は、
ここに写っているアダプターを介して組み合わせた場合、
ヘリコイド繰り出し量にして約1〜2mm分のオーバーインフでした。
これを言い換えれば、レンズとフィルム面の離隔距離がもう少し大きくても、
無限遠にピントを合わせることが可能と言うことですね。
一方、一眼レフカメラのフランジバックについて調べてみると、
・写真左:ペンタックスSV(M42)が、45.5mmに対して、
・写真右:ニコンF2は、46.5mmとわずか「1mm」長いだけです。
ということは、
前回のオーバーインフ約1〜2mm分が生きてきます。
「ニコンF2」と、前回の「組み合わせレンズ」との間に、
何かその程度の厚みのものを挟み込んでも、
無限遠にピントが来るわけです。
そこに期待して、M42→Nikon_F のアダプターを買ってみました。
『Pixco マウントアダプター M42レンズ-Nikon カメラボディー対応』
という商品です。
当然中国製の格安品、送料込みの 619円でした。
厚みは約1mm。
挟み込むのにちょうど良いアダプターのはずです。
今回は、ニコンF2のボディに対してではなく、
一足飛びに「Sonyα7II」に装着してしまいました。
それでも、特に難しいことはなく、
・Nikon F → Leica M
・Leica M → NEX
を余分につけるだけですね。
すなわち、次の写真の左側の二つを付け足しただけです。
全部組み合わせたのが次の状態。
何か寸詰まりの恐竜のような形ですが、
これが、「AF仕様に変貌したNikkor引伸しレンズ」の姿です。
カメラに装着するとこう。
ほんの僅かヘリコイドを繰り出してあげると、
無限遠が出ました。
想定通りです。
その状態で、あとはノータッチ、
完璧なオートフォーカスができました。
絞りをF5.6に設定し、あとは全てAutoで撮った実写例。
・明治通りの銀杏並木
・日出優良商店会の居酒屋
・同じく蕎麦屋「あさひ」(ここで昼食)
・公園のキャッチボール
・出来立てホヤホヤの「イケバス」
・イケバスに再度遭遇
最後の一枚が動体ボケしていますが、
それ以外は、キレキレの写りです。
「EL-Nikkor 1:4 75mm」は、
もともと6x6フィルム用の引伸しレンズなので、
普通のフルサイズイメージに対しては余裕ありすぎなくらいです。
ちなみに、この状態のExifは次のように記録されていました。
このうち注意しなければいけない点は、次のとおり。
・露光量は実絞り(今回はf/5.6)に関係なくf/2.0と表記されてしまう。
・レンズ焦点距離はLM-EA7での任意の設定値が記録される。
この設定値によりボディ内手ブレ補正が働くので、一応設定してみた。
ただし、75mmという選択肢は無いので、それに近い90mmを選択した。
・レンズ名はなぜかこのように表記された(LM-EA7とすれば良いのに?)
まあ、撮影記録として何かの役に立つとしたら、
シャッタースピードとISO値、でしょうか。
(続く)
6年前の明治通りの風景 ― 2019年12月18日
(前回)からの続きです。
「PentaxSV」+「EL-Nikkor 1:4 75mm」という、
普通ではあり得ない組み合わせで撮影した中の一コマに、
次の風景がありました。
明治通りを、学習院下付近の歩道橋から撮影したものです。
同じ「PentaxSV」に標準レンズ「55mm 1:1.8」をつけて、
6年前に撮影した次のものと比較してみましょう。
それぞれ、12月と2月の写真なので、
イチョウの葉の様子が違うのは当然として、
それ以外の一番大きな違いは、正面の超高層ビルが、
サンシャイン60から豊島区役所(マンション併設)に変わったことです。
(サンシャイン60は消えたわけではなく、後ろに隠れています)
また、道路左側のイチョウが伐採され、
歩道が中学校の敷地側に拡幅されていることも目立ちます。
この道路の現状は「環状第5の1号線」事業による仮の姿で、
数年後には、ここの風景は大変貌を遂げるはずです。
(道路中央部の二車線が掘割形式になるそうです)
に記しました。
そうなることが決まっているなら、
その姿を早くみてみたいですね。
そして、その新しい風景を、今度はどんなカメラで撮影することになるのか、
今からちょっと楽しみです。
ちなみに、完成イメージが東京都建設局のHPに載っていました。
区役所の裏に隠れたはずのサンシャイン60が、
再度立派な姿を見せています。
本当にこの通りの風景にするなら、
豊島区役所の超高層ビルを、解体撤去しなければなりません。
笑える。
掘割部の断面図は次の通り
(続く)
PentaxSVに引伸し機用レンズ ― 2019年12月16日
各種レンズアダプターで遊んでいるうちに、
6年前に修理したフィルムカメラの「PentaxSV」に、
引伸し機用レンズの「EL-Nikkor 1:4 75mm」を装着して、
撮影できることを発見しました。
7年前にオリンパスPEN E-P3にて使用した
「BORGアダプター」の再利用です。
この時は、次のような組み合わせで撮影していました。
今考えると、高価でものすごく贅沢な組み合わせです。(ほとんどバカ)
今回はそのうち、次のものを使用してみました。
これで、M42マウントのカメラでピント合わせができるのです。
若干オーバーインフ気味になりますので、
ヘリコイドを1〜2mm繰り出してやると、無限遠にピントが来ます。
最短では3mほどまで近づけます。
露出計とフードを装備して臨戦態勢を整えました。
うまい具合に二眼レフ「Ricoh FLEX」の被せ式フードがピッタリでした。
手持ちの機材だけでも、工夫すれば色々遊べるものですね。
フィルムを詰めて、早速、目白のイチョウを撮影に。
そして現像。
なかなか良さげ!
明治通りのイチョウが丁度見頃でした。
千登世橋の上では、
「都電とイチョウ」に挑戦しているカメラマンが多数。
目白不動金乗院の敷地にも、敷き詰められたような落ち葉。
鬼子母神のイチョウも、もちろん見頃。
午後の日差しがイチョウを美しく見せていました。
(続く)





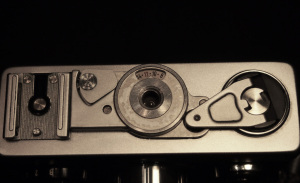
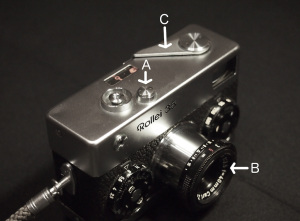


























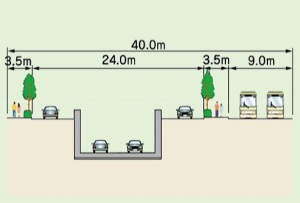











最近のコメント