▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます
・目白の風景 今昔:目次
・吉祥寺の風景 今昔:目次
・昔と今の写真(番外編):目次
・地中海バブル旅行etc.:目次
・旅のつれづれ:目次
・母のアルバム:目次
・目白ジオラマ鉄道模型:目次
・すべてのカメラに名前がある:目次
・目白の風景 今昔:目次
・吉祥寺の風景 今昔:目次
・昔と今の写真(番外編):目次
・地中海バブル旅行etc.:目次
・旅のつれづれ:目次
・母のアルバム:目次
・目白ジオラマ鉄道模型:目次
・すべてのカメラに名前がある:目次
上り屋敷駅と踏切(2) ― 2012年08月02日
(前回)からの続きです。
目白駅から上り屋敷公園へ向かう最短ルートに、西武池袋線の小さな踏切が一つあります。「上り屋敷駅」跡のすぐ東側になります。1970年代の私もこの踏切を毎日のように通っていました。住宅街にふさわしくヒューマンなスケールの踏切なのですが、通勤通学時間帯は電車の本数がとても多く、良く待たされた記憶があります。1974年1月末の夕方も電車の通過待ちをしていました。
一緒に待っている三人のうち、左側のチェックのコートの少女はこれから塾かお稽古事にでも行くのでしょうか?手提げ鞄を持っています。「電車、早く行っちゃわないかな。間に合わなくなっちゃう」と思っているようです。バーが開くと急いで右側の道へ駆けて行きました。
線路敷と道を隔てる柵は枕木の再利用です。昔はみんなこれでしたね。懐かしい風景です。
この二枚の写真と同じ撮影位置で2012年の風景を撮ってみました。まず踏切です。
この二枚の写真と同じ撮影位置で2012年の風景を撮ってみました。まず踏切です。
今も中央に白杭が立っていて車は通れないようになっています。踏切のサインや警告灯など風景の構成要素はほとんど新しいものになっていますが、何と驚き!左側のおうち(土屋電子という表札がかかっていました)が昔のままでした。現在の写真の赤い丸で囲った部分が窓の小庇と木製横格子です。ちょっと撓んでいますが頑張って窓をガードしています。38年間ご苦労さん。
次は線路沿いの道の現在の写真です。
次は線路沿いの道の現在の写真です。
さすがに昔の枕木製柵はコンクリート基礎のネットフェンスに変わっています。だいたい今時、木製の枕木なんて使われていませんからね。
左の民家の塀はどうかな?と思って眺めてみて、これは本当にビックリしました。写真に写っている竹垣が本物の竹を使った「建仁寺垣」なのです。昔と全く同じです。38年前はともかく現代の都心の住宅で本格的な竹垣を見ることはまれです。和風建築の守り手としての家主さんの心意気に感激です。
昔と今の風景を見比べると、面白くて嬉しいことが時々あります。
左の民家の塀はどうかな?と思って眺めてみて、これは本当にビックリしました。写真に写っている竹垣が本物の竹を使った「建仁寺垣」なのです。昔と全く同じです。38年前はともかく現代の都心の住宅で本格的な竹垣を見ることはまれです。和風建築の守り手としての家主さんの心意気に感激です。
昔と今の風景を見比べると、面白くて嬉しいことが時々あります。
(この項、終り)
シャッター速度と手ぶれ ― 2012年08月05日
撮影に失敗した写真の形容詞として「ブレ・ボケ」という言葉があります。ボケボケ写真やブレブレ写真は撮りたくないものです。フィルム時代にはDPEから上がってきた写真を見てがっかりしたことも再三ありました。
最近のデジカメは手ぶれ補正機構が備わっているので、若干の手ぶれは救ってくれます。
しかしバルナックライカなどの昔のカメラを使用する場合、シャッター速度と絞り値を適切に選択しなければ直ちに失敗写真となります。
意図せざるボケを防ぐために絞りを絞ってピントの合う範囲を広げることが出来ます。しかし、その場合はシャッター速度は遅くせざるを得ないので、ブレの確率が高まります。
そこで課題。手持ち撮影をする場合、何分の1秒までは手ぶれせずに撮影できるか?
何十年も前、マニュアルカメラが普通であった時代は撮影時の心構えとして次のように言われていました。
・1/30秒以上の速度を選び、重心を低くし脇を締めて静かにシャッターボタンを押す
・プロは1/8秒まで手ぶれせずに撮影できる(真偽のほどは不明)
今後の参考に、ちょっとした撮影テストをして私の身体能力を試してみることにしました。
最近のデジカメは手ぶれ補正機構が備わっているので、若干の手ぶれは救ってくれます。
しかしバルナックライカなどの昔のカメラを使用する場合、シャッター速度と絞り値を適切に選択しなければ直ちに失敗写真となります。
意図せざるボケを防ぐために絞りを絞ってピントの合う範囲を広げることが出来ます。しかし、その場合はシャッター速度は遅くせざるを得ないので、ブレの確率が高まります。
そこで課題。手持ち撮影をする場合、何分の1秒までは手ぶれせずに撮影できるか?
何十年も前、マニュアルカメラが普通であった時代は撮影時の心構えとして次のように言われていました。
・1/30秒以上の速度を選び、重心を低くし脇を締めて静かにシャッターボタンを押す
・プロは1/8秒まで手ぶれせずに撮影できる(真偽のほどは不明)
今後の参考に、ちょっとした撮影テストをして私の身体能力を試してみることにしました。
・使用機材:オリンパスペン E-P3 + 中望遠レンズM.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8
・撮影対象:遠方の高層ビルを、シャッター速度 1/8 と 1/30 にて撮影
・また、参考までにカメラの手ぶれ補正機構オン・オフの二通りで撮影しました。
結果1.シャッター速度 1/30 手ぶれ補正オン(中央部切り出し、以下同じ)
・撮影対象:遠方の高層ビルを、シャッター速度 1/8 と 1/30 にて撮影
・また、参考までにカメラの手ぶれ補正機構オン・オフの二通りで撮影しました。
結果1.シャッター速度 1/30 手ぶれ補正オン(中央部切り出し、以下同じ)
結果2.シャッター速度 1/30 手ぶれ補正オフ
結果3.シャッター速度 1/8 手ぶれ補正オン
結果4.シャッター速度 1/8 手ぶれ補正オフ
結論としては、私にはプロの技量はないことが分かりました。1/30秒は補正なしでも合格ですが、1/8秒は補正があって何とか見られる出来です。最新のデジカメでないカメラを使う場合は、昔教えられた通り、常に1/30秒以上で撮影することにしました。
近衛町からおとめ山公園へ(1) ― 2012年08月10日
目白駅の南西、住所で言うと新宿区下落合のあたりは「近衛町」と呼ばれています。道の真ん中に欅の大木がある所、と説明すると多くの人が「あそこか」と思いあたるようです。
この辺りは「上り屋敷」よりも更に高級な住宅地です。約40年ほど前に「下落合シティハウス」なる低層の高級マンションが建設され、その価格にビックリしました。このマンションも最近は手が届く価格で売り出されているようですが、管理費などがやたら高く相変わらず庶民には縁遠い物件です。
最近は相続の関係からか個人住宅から中規模マンションへ建替えられる例が多く、その建物名称として「近衛町」が好まれています。ちょっと高級な感じがしますよね。
実際、高額物件が多く、造りも贅沢で区の保護樹木を玄関周りに取込んでいる例などがあります。
最近は相続の関係からか個人住宅から中規模マンションへ建替えられる例が多く、その建物名称として「近衛町」が好まれています。ちょっと高級な感じがしますよね。
実際、高額物件が多く、造りも贅沢で区の保護樹木を玄関周りに取込んでいる例などがあります。
立派なスダジイですね。
もちろん個人の住宅も沢山残っていて、良い雰囲気の街並みを形成しています。その中に「アレ?」と思う住宅がありました。何か訴えかけるものがあったのです。
昔の写真を探してみると、こんな写真がありました。
38年前に「モダンな住宅だな」と感心して撮影したようです。建物にはいくつか手が加えられていますが、今でも十分素敵ですね。
この地域には「目白ヶ丘教会」というバプテスト派の教会があります。このような宗教施設が立地する所は地域のイメージが良くなりますね。近衛町もそんな感じです。
この地域には「目白ヶ丘教会」というバプテスト派の教会があります。このような宗教施設が立地する所は地域のイメージが良くなりますね。近衛町もそんな感じです。
この日もよい天気で、建物脇の良く手入れされた花壇にはキアゲハが戯れていました。良く見ると青サルビアの蜜を吸いに来ているようです。
かなり接近して撮影した所、蝶の複眼と眼が合ってしまいました。いわゆる見つめ合った状態です。動物と眼が合うことは良くありますが、蝶々とは始めてです。近衛町のキアゲハらしく結構尊大な眼をしていました。
さて先ほどの「近衛の欅」を南下すると都選定歴史的建造物として名高い「日立目白クラブ」があります。分離派建築的スパニッシュスタイルとでも言うべき面白い建物です。残念ながら現在改修中でしたので、いずれ改めて取り上げてみたいです。
(翌年、見学してきました。その記録はこちらです。)
工事用シートの貼り方も表現主義的な感じがしていて可笑しかったです。
さて先ほどの「近衛の欅」を南下すると都選定歴史的建造物として名高い「日立目白クラブ」があります。分離派建築的スパニッシュスタイルとでも言うべき面白い建物です。残念ながら現在改修中でしたので、いずれ改めて取り上げてみたいです。
(翌年、見学してきました。その記録はこちらです。)
工事用シートの貼り方も表現主義的な感じがしていて可笑しかったです。
この塀に沿って右手、西方へ歩いて行くと急な階段が現れて、その向こうに「おとめ山公園」が広がっています。
.....(続く)
近衛町からおとめ山公園へ(2) ― 2012年08月12日
(前回)からの続きです。
おとめ山公園は坂道を挟んで東と西に分かれています。日立目白クラブ側からアクセスすると、まず東側のエリアに入ります。こちらには弁天池があって、何十年も前から生息していたかのような亀もいます。
おとめ山公園は坂道を挟んで東と西に分かれています。日立目白クラブ側からアクセスすると、まず東側のエリアに入ります。こちらには弁天池があって、何十年も前から生息していたかのような亀もいます。
東側のエリアを抜け西側へ入るには、管理棟に近い坂下側の入口を使います。坂上にも下の写真のような立派な門がありますが強度的な問題により現在は閉鎖中です。
38年前はこんな感じで使われていました。手前の電話ボックス以外ほとんど同じですね。
西側エリアは雑木林とせせらぎで構成される武蔵野の森です。森の景色は以前ライカで撮影したものを紹介しましたので、ここでは公園南西側の崖に面する見晴し台に触れてみたいと思います。管理棟から左手に緩やかな階段とスロープがあります。
これを登りきると高台に出ます。その一角に四阿(あずまや)があります。
ここは訪れる人が少なく、38年前の冬の日に来た時もジャージ姿で柔軟体操をしている男性が一人いただけでした。
先日訪れた時も、一匹の猫が切株の上で休んでいるだけでした。
高台からは下落合の街並を見下ろすことが出来ます。ネットフェンスとそれに絡まるツタがちょっと邪魔です。
おとめ山公園の周辺には公務員住宅が沢山ありました。住まうにはとても良い環境で羨ましかったですが、現在は解体中です。
跡地は新宿区が買取りおとめ山公園と一体で整備するそうです。楽しみですね。
孫のフォトブック自作 ― 2012年08月14日
昨年三月中旬に福島原発で水素爆発が起きた時、我が家では娘が出産のために里帰りしていました。予定日を約一ヶ月後に控え、近くの聖母病院で出産予約を済ませ、子どもが生まれる気になるのを待つばかりでした。ところが爆発。その後の政府と東電の対応から、原発がほとんど制御不能に陥っていると感じた私は、東京も放射能で汚染されるのではと心配になりました。
ただちに娘の夫の実家がある中部に「疎開」させることにしました。病院には事情を話して転院の手続きをお願いしました。すると驚いたことに、病院側は「ああして、こうして」と実に簡潔明瞭に必要な手続きを説明してくれました。怪訝に思った私がたずねると、病院さんが言うには、同じように東京から逃げ出す妊婦さんが続出しているとの事でした。
とてもアットホームな病院で、娘もすっかり信頼していたのに、こういう理由で転院手続きがルーチン化する病院ってあり得ないですよね。とにかく聖母病院さん、ありがとうございました。疎開した娘は翌月、無事に初子を産みました。
ただちに娘の夫の実家がある中部に「疎開」させることにしました。病院には事情を話して転院の手続きをお願いしました。すると驚いたことに、病院側は「ああして、こうして」と実に簡潔明瞭に必要な手続きを説明してくれました。怪訝に思った私がたずねると、病院さんが言うには、同じように東京から逃げ出す妊婦さんが続出しているとの事でした。
とてもアットホームな病院で、娘もすっかり信頼していたのに、こういう理由で転院手続きがルーチン化する病院ってあり得ないですよね。とにかく聖母病院さん、ありがとうございました。疎開した娘は翌月、無事に初子を産みました。
その私にとっての初孫が東京へ来ました。初の長旅です。両親の夏休みを利用し、娘のお腹にいる時から起算すると、約一年と五ヶ月ぶりの来京です。約300枚の写真を撮り、その中から選りすぐった60枚でフォトブックを作ることにしました。
上の写真はMacでフォトブックを作成している所です。Mac付属のソフトiPhotoでは、画像の取込み、編集加工、写真管理がこの一つのソフト上で出来るだけでなく、写真の選定からフォトブックの作成までも一遍にこなせます。そして何と編集画面の右下の『ブックを購入』のボタンを押すだけで、Appleストアから完成したフォトブックが送られてきます。そして後日、数千円の利用明細がカード会社から届きます。
問題は価格ですね。その出来栄えからすれば安いとも思いますが、いろいろなフォトブックを作りたい私にしてみれば、何とかしたい所。そこで、あれこれ調べて自作する方法を考えました。また、完成後もページの追加・削除・差し替えが可能なリング製本方式を選択しました。
以下の方法によれば初期投資以外はインクやペーパーの消耗品代だけで、実にお安くフォトブックを作成できます。
■手順1:機器を購入
問題は価格ですね。その出来栄えからすれば安いとも思いますが、いろいろなフォトブックを作りたい私にしてみれば、何とかしたい所。そこで、あれこれ調べて自作する方法を考えました。また、完成後もページの追加・削除・差し替えが可能なリング製本方式を選択しました。
以下の方法によれば初期投資以外はインクやペーパーの消耗品代だけで、実にお安くフォトブックを作成できます。
■手順1:機器を購入
今の日本ではほとんど選択肢はありません。多分、カール事務器の「コームゲージパンチセット TZ-20G」しか無いでしょう。Amazonで5,000円くらいで売っています。
この商品のシステム名はTOZICLE(トジックル)というそうです。なかなかユニークですね。
写真の上から順に次の商品がセットされています。
1.コームセットアップ
2.パンチ
3.ゲージ
4.コームリング(消耗品ですが付属で6本付いています)
その他に製本カバー18枚が消耗品として付いていますが今回は使用しません。
■手順2:フォトブック作成編集
これはiPhotoにて実行します。ほとんど自動的に済んでしまいます。
■手順3:A4サイズの用紙にプリント
表紙用には厚手の用紙を使うと良いです。今回は0.22mm厚を使用。
表紙以外の中身に使う用紙は少し薄くすると全体がかさばらないです。今回は0.185mm厚の商品を使いました。
■手順4:用紙に穴あけ
この商品のシステム名はTOZICLE(トジックル)というそうです。なかなかユニークですね。
写真の上から順に次の商品がセットされています。
1.コームセットアップ
2.パンチ
3.ゲージ
4.コームリング(消耗品ですが付属で6本付いています)
その他に製本カバー18枚が消耗品として付いていますが今回は使用しません。
■手順2:フォトブック作成編集
これはiPhotoにて実行します。ほとんど自動的に済んでしまいます。
■手順3:A4サイズの用紙にプリント
表紙用には厚手の用紙を使うと良いです。今回は0.22mm厚を使用。
表紙以外の中身に使う用紙は少し薄くすると全体がかさばらないです。今回は0.185mm厚の商品を使いました。
■手順4:用紙に穴あけ
ゲージに数枚ずつ用紙を挟み、パンチで穴をあけて行きます。パンチの凸部とゲージの凹部が噛み合って正しい位置に穿孔されます。
■手順5:リングを開く
■手順5:リングを開く
コームセットアップにリングをセットし、付属のロッドを右からリングの円の中に押し込んで行きます。
■手順6.製本
■手順6.製本
開いたリングに束ねた用紙をセットし、手順5と逆にロッドを引き抜いて行います。用紙の穴の中にリングの先端が左から順番に入って行きます。
■手順7.完成
■手順7.完成
余分のリングをはさみで切り落とし、光り輝くリング製本の完成!
手順4〜6を再度行うことによってページの追加・差し替えが可能です。既成のフォトブックと違ってとても便利ですよ。
(注意点)
手順4の用紙の穴あけを効率的に済ませたい方には
コームグリッサーセット TZ-20S がお薦めです。
当然価格は高く9,000円程度になります。沢山作る人には一考に値するかな。
また、手順5と6の仕組みを理解してる方にはコームセットアップは「あれば便利、無くても可」という商品です。実際にこれを省いた「パンチとゲージ」だけのGPS-20という商品も2,000円くらいでありました。でもこれを注文しても、納期未定の返事が来ます。残念。
こういう分野が得意なはずの東急ハンズにもこの商品は置いてなかったです。四角い穴でなくルーズリーフ用の丸い穴をあける機器もこのメーカーは作っています。そっくりです。これは普通に販売されているので間違って買わないように。商品の型番に注意して間違いない商品を購入することが、この一連の作業の山場だったりします。ルーズリーフ用だけ東急ハンズにあるということは多分学生さんの需要があるのでしょうね。リング製本って、プレゼン資料の作成などで業務用としては結構需要があると思うのですが、個人が趣味で使うことは稀なのかな?
追加用のコームリングは、6、8、10、13mmがそれぞれ10本組でネットショップでお安く手に入ります。多分送料の方が高くなるくらいでしょう。リングのサイズはアラウアンスがあるので、普通の製本なら、8mmまたは10mmでほとんど済んでしまいます。
手順4〜6を再度行うことによってページの追加・差し替えが可能です。既成のフォトブックと違ってとても便利ですよ。
(注意点)
手順4の用紙の穴あけを効率的に済ませたい方には
コームグリッサーセット TZ-20S がお薦めです。
当然価格は高く9,000円程度になります。沢山作る人には一考に値するかな。
また、手順5と6の仕組みを理解してる方にはコームセットアップは「あれば便利、無くても可」という商品です。実際にこれを省いた「パンチとゲージ」だけのGPS-20という商品も2,000円くらいでありました。でもこれを注文しても、納期未定の返事が来ます。残念。
こういう分野が得意なはずの東急ハンズにもこの商品は置いてなかったです。四角い穴でなくルーズリーフ用の丸い穴をあける機器もこのメーカーは作っています。そっくりです。これは普通に販売されているので間違って買わないように。商品の型番に注意して間違いない商品を購入することが、この一連の作業の山場だったりします。ルーズリーフ用だけ東急ハンズにあるということは多分学生さんの需要があるのでしょうね。リング製本って、プレゼン資料の作成などで業務用としては結構需要があると思うのですが、個人が趣味で使うことは稀なのかな?
追加用のコームリングは、6、8、10、13mmがそれぞれ10本組でネットショップでお安く手に入ります。多分送料の方が高くなるくらいでしょう。リングのサイズはアラウアンスがあるので、普通の製本なら、8mmまたは10mmでほとんど済んでしまいます。






























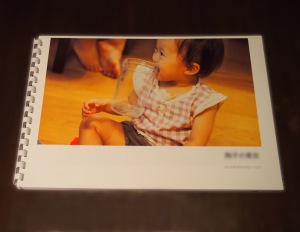
最近のコメント