▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます
・目白の風景 今昔:目次
・吉祥寺の風景 今昔:目次
・昔と今の写真(番外編):目次
・地中海バブル旅行etc.:目次
・旅のつれづれ:目次
・母のアルバム:目次
・目白ジオラマ鉄道模型:目次
・すべてのカメラに名前がある:目次
・目白の風景 今昔:目次
・吉祥寺の風景 今昔:目次
・昔と今の写真(番外編):目次
・地中海バブル旅行etc.:目次
・旅のつれづれ:目次
・母のアルバム:目次
・目白ジオラマ鉄道模型:目次
・すべてのカメラに名前がある:目次
ライカの低速シャッター ― 2016年06月07日
使用するときは、高速用ダイアルを1/25秒に合わせた上で、
この低速用を右に回して、1/15秒または1/10秒、
左に回して、1/5秒、1/2秒または1秒に合わせます。
この面倒な仕様を現役で体験している人は、
もうほとんど生存していないでしょう。
だからこそ、今更フィルムカメラを使うなら、この二軸式ダイアルも面白いです。
いわゆる「カメラの歴史」を学ぶという感じですね。
今回の分解で、この低速シャッターのメカニズムを勉強してみると、
ほとんど職人技というか手作り感満載でした。
低速シャッターの速度を司るのは、基本的にスローガバナーです。
(これはその後の数十年間、電子式シャッターが生まれるまで不変でした)
この低速用を右に回して、1/15秒または1/10秒、
左に回して、1/5秒、1/2秒または1秒に合わせます。
この面倒な仕様を現役で体験している人は、
もうほとんど生存していないでしょう。
だからこそ、今更フィルムカメラを使うなら、この二軸式ダイアルも面白いです。
いわゆる「カメラの歴史」を学ぶという感じですね。
今回の分解で、この低速シャッターのメカニズムを勉強してみると、
ほとんど職人技というか手作り感満載でした。
低速シャッターの速度を司るのは、基本的にスローガバナーです。
(これはその後の数十年間、電子式シャッターが生まれるまで不変でした)
そして、低速ダイアルとガバナーは、複雑な機構で連動していました。
この写真の前シャーシを外して裏側を見てみると、
次のように、縦長の「ロッド」と真鍮削りだしの「突起」が見えます。
次のように、縦長の「ロッド」と真鍮削りだしの「突起」が見えます。
突起はダイアルと同軸になっていますが、
中心から外周部までの距離が変化しているので、
ダイアルを回すと、突起と接するロッドは左右に振れます。
そしてロッドの先端の動きは、次のガバナーのレバーに伝わります。
中心から外周部までの距離が変化しているので、
ダイアルを回すと、突起と接するロッドは左右に振れます。
そしてロッドの先端の動きは、次のガバナーのレバーに伝わります。
レバーが右にあるときはガバナーの抵抗は重く、左にあると軽くなります。
また、「突起」の先端は波打っているので、
この先端で抑え込まれる「スロー連動棒」は、
ダイアルのセット位置によって少しずつ前後し、
ガバナーから動作制限を受ける度合いが変化します。
そして、この連動棒が、
最終的にシャッターの後幕が走り出すタイミングを決めるので、
これらが総合的に関係して、1/25秒〜1秒の低速シャッターが実現します。
と文章にしても全く解説になっていませんね。
まあ、こんな感じの綱渡りのような工夫で実現されている低速なので、
ライカの中古品には、この低速シャッターが機能していないものがあります。
再組み立てしてシャッターが甦ったはずの当機もそうでした。
ただ私の場合は、整備不良というよりも、
とんでもないポカをやっていた事が原因でした。
それは良くあるミスらしいです。
ガバナーを取り出してベンジン浴をしている間に
ぜんまいバネが外れてしまっていたのです。
また、「突起」の先端は波打っているので、
この先端で抑え込まれる「スロー連動棒」は、
ダイアルのセット位置によって少しずつ前後し、
ガバナーから動作制限を受ける度合いが変化します。
そして、この連動棒が、
最終的にシャッターの後幕が走り出すタイミングを決めるので、
これらが総合的に関係して、1/25秒〜1秒の低速シャッターが実現します。
と文章にしても全く解説になっていませんね。
まあ、こんな感じの綱渡りのような工夫で実現されている低速なので、
ライカの中古品には、この低速シャッターが機能していないものがあります。
再組み立てしてシャッターが甦ったはずの当機もそうでした。
ただ私の場合は、整備不良というよりも、
とんでもないポカをやっていた事が原因でした。
それは良くあるミスらしいです。
ガバナーを取り出してベンジン浴をしている間に
ぜんまいバネが外れてしまっていたのです。
このように教科書でも注意を促されていたのに!!
やはり、教科書は謙虚な心で良く読むべきですね。
このミスに気づいて、ぜんまいバネの位置を修正した後は、
低速シャッターもそれなりの速度で切れるようになりました。
1秒にセットして動画に撮りました。
それでも、ちょっと長く1.3秒くらいになってますね。
実は、この動画の後、
もう一度ガバナーをベンジンで洗い、教科書の教えに従って、
ベンジンで希釈した精密油をほんの少し歯車軸にさしたら、
かなり1秒に近くなりました。
教科書ってたいせつです。
(続く)
やはり、教科書は謙虚な心で良く読むべきですね。
このミスに気づいて、ぜんまいバネの位置を修正した後は、
低速シャッターもそれなりの速度で切れるようになりました。
1秒にセットして動画に撮りました。
それでも、ちょっと長く1.3秒くらいになってますね。
実は、この動画の後、
もう一度ガバナーをベンジンで洗い、教科書の教えに従って、
ベンジンで希釈した精密油をほんの少し歯車軸にさしたら、
かなり1秒に近くなりました。
教科書ってたいせつです。
(続く)

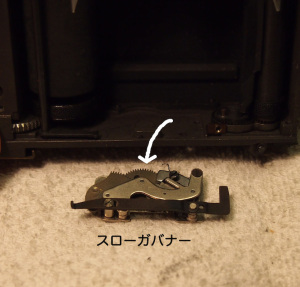


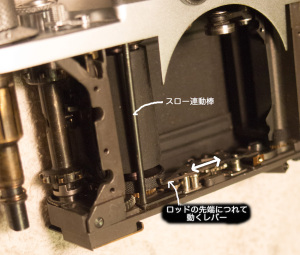

最近のコメント