▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます
・目白の風景 今昔:目次
・吉祥寺の風景 今昔:目次
・昔と今の写真(番外編):目次
・地中海バブル旅行etc.:目次
・旅のつれづれ:目次
・母のアルバム:目次
・目白ジオラマ鉄道模型:目次
・すべてのカメラに名前がある:目次
・目白の風景 今昔:目次
・吉祥寺の風景 今昔:目次
・昔と今の写真(番外編):目次
・地中海バブル旅行etc.:目次
・旅のつれづれ:目次
・母のアルバム:目次
・目白ジオラマ鉄道模型:目次
・すべてのカメラに名前がある:目次
60年経っても完動のニコンNikon_S2 ― 2019年09月16日
ニコンのレンジファインダー機で遊んでみることにしました。
入手した個体は「ニコン Nikon S2」の後期型ブラックダイアル。
この型は、同シリーズ(S2・SP・S3・S4)の中では古い製品のためか、
状態が良い割には安価でした。
・標準レンズはカビ・クモリなく、
・カメラ本体の外装も綺麗で大きな傷なく、
・シャッターも全速快調で、
・ファインダーはクリア、
・連動距離計の二重像もバッチリ、でした。
古いレンジファインダー機の場合、ファインダーが曇っていたり、
二重像が薄くなって見えにくくなっている個体が普通なので、
ここまでファインダーの状態が良いのは、
「ラッキー!」としか言いようがありません。
何しろ製造されたのは1957年頃です。
どこかの時点で丁寧にオーバーホールされたのでしょう。
早速、フジのアクロスAcros100を詰めて、
雨上がりの目白を、20枚ほど Walk & Shoot。
現像してみると、程よい濃度のネガに仕上がりました。
ピントの精度も良好でした。
年代モノのレンズにしては逆光の画像もキリッとしていました。
いくつかピックアップしてみます。
(続く)
ニコンNikon_S2の臨戦態勢 ― 2019年09月22日
(前回)からの続きです。
ニコンS2で Walk & Shoot するには準備が必要です。
私の場合、まず「レンズフード」。
綺麗な写真を撮るためには必須のアイテムです。
また、フードは、レンズの前玉の保護にも役立ちます。
調べてみると、
標準レンズの " Nikkor 50mm f2 " のフィルタ径は40.5mmで、
これは次の写真左側の「ミノルタCLE」の標準レンズと同サイズでした。
と言うことは、今CLEに付いているフード、これが流用できますね。
それから、露出計。
これも、次の写真左側の「ライカⅢG」に装着している、
クリップオン型の露出計(フォクトレンダーのVCメーターⅡ)。
これが使えるはずです。
ところが、ニコン Nikon S2に取り付けてみると、
このように、フィルム巻き上げノブとメーターが干渉してしまいました。
一瞬ダメかと思いましたが、この露出計は良くできていて、
次のように、取り付けネジを付け替えてシューを移動し、
干渉を回避することができました。
そんなわけで、特に余分な出費を要せず、臨戦態勢が整いました。
ついでに、シャッターボタンを押しやすくするために、
「ニコン Nikon F」用のソフトレリーズも取り付けましたよ。
こんなカメラを手にすると、お散歩に行きたくなります。
(一旦終了)
Minox_TLXの修理 ― 2019年09月28日
数ヶ月前のこと、
「ACMEL-Mは不滅です」のブログ記事の中で、
「簡単なカメラは壊れないのが強みです」と書いた、丁度その頃、
私のもう一つのMinoxは危機に陥っていました。
次の写真、右側が不滅のACMEL-M、
左側が問題のMinoxTLXです。
この頃、ACMELで撮影したネガは、こんな風でした。
カンを頼りに露出を決めても、そこそこ適正なネガ濃度です。
ところが、TLXで撮影したものは、
次のように一部に露光不良のコマが生じました。
撮影状況を思い出しながら、撮影結果と比較して考察すると、
明るいところで撮影したコマが、
なぜか極端な露光不足になっているようでした。
普通は逆ですよね。
そこで思い出したのは、フォーカルプレーンシャッターの不具合。
ライカなどでも、1/500とか1/1,000秒の高速シャッターについて、
シャッターが開かない事例が少なからずあるようです。
実際、私が自らメンテした " ライカ Ⅲf " も、
1/1,000秒の場合、
画面の片側が少し暗めの仕上がりになりました。
確か、Minoxのシャッターもギロチン式でしたから、
原理はフォーカルプレーンと同じです。
先幕と後幕の走り出すタイミングと走行速度の調整が狂うと、
開かない、あるいは露光ムラ、という不具合が生じるはずです。
ちなみに、私のミノックスTLXは、レンズの絞りはf3.5の固定。
AEの調節は全てシャッター速度の変更で行うタイプです。
ということは、
明るい場所ので撮影 → 高速シャッター → きちんと開かず
という因果関係が成り立ちそうです。
そんな具合に、故障の原因は何となく推察できましたが、
「では、どうする?」
対応策は次のようなものが考えられます。
[1]諦めて、もう使わない。
[2]故障品のまま売っぱらう。
[3]自ら分解修理に挑戦する。
[4]プロに修理を頼む。
どれも選び難いです。
なぜなら、それぞれ、次のような問題があるからです。
[1]もったいない。
[2]どうせ二束三文にしかならない。
[3]こんな精密なもの、壊すのがオチ。
[4]高額な修理料金を取られそう。
さんざん悩んだ挙句、[4]のプロの修理を選択しました。
カメラ修理で、他人の力を借りるのは初めてです。
(続く)
Minox_TLXで撮影 ― 2019年09月30日
(前回)からの続きです。
プロに修理をお願いしてから約4ヶ月後、
修理完了の報告がありました。
発注時に、
「修理をお急ぎの場合は、その旨お知らせください」
とは連絡を受けていましたが、
特に完了時期の希望は出していなかったので、
まあ、成り行きで4ヶ月かかったのだと思います。
「その旨」と言われたって、今時、
フィルムカメラの修理を急ぐ理由などあるわけないし。
費用は、当初の見積りどおりで、二万円弱。
「平日ゴルフ2回分と思えば、妥当な金額かな?」と自ら納得させました。
問題は、治っているかどうか。
高速シャッターは、
外から見ただけでは開いているかどうか分からないので、
試写が必要です。
これは試写のために、フィルムを詰めているところです。
このフィルムは自作です。
40年ぶりにMinoxを使い出した6年前は、
フィルムも細々と市販されていました。
現像とプリントも、ビックカメラが受け付けていました。
このようなMinoxミノックスの使用環境は、
今では壊滅しているでしょう。
でも、
私の場合は、自らMinoxフィルムを「作り・現像する環境」を整えたので、
せっかく整えたその環境を失うわけにはいきません。
だから、二万円もかけてMinox_TLXを修理したのですね。
さて、フィルムの原材料は、35mm用のFuji_Across100。
Nikon_S2で半分ほど撮影した残りです。
二組のカートリッジに詰めて、
30枚撮りMinoxフィルムが二本できました。
そして散歩がてらの試写。
撮影が済んだら現像。














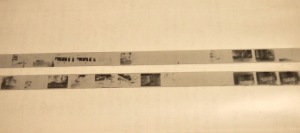






最近のコメント